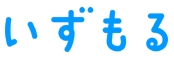大社の町で数少ないお寿司屋さんが、出雲大社の境内入り口の勢溜(せいだまり)から、歩いてわずか3分あまりのところにある。その名は浪花鮓。鮓と書いて「すし」と読むので「なにわずし」である。鮓、鮨、寿司の由来は奥深いのでここでは触れないが、昭和の遷宮があった昭和28年に、今の店主の服部(はっとり)さんの祖父が再開した、もっぱら出前に軸足を置いた寿司屋だったそうだ。だから鮓なのかもしれない。
寿しの文字のある赤い提灯(ちょうちん)が下がっている浪花鮓の玄関の戸を、ガラガラと引いて中に入ると、分厚い木のカウンターが伸びている。さらにカウンターの上には屋根も付いている。この伝統的な寿司屋の作りは、江戸前の握り寿しが、もともとは屋台だったことに由来する。
さっそくカウンターに陣取り、お願いしたのは握りの並7貫盛り1,730円(税込)である。服部さんの握った赤身のヨコワ(マグロの若魚)、カンパチ、ウナギ、イカ、カニ、エビ、イクラと並んでいる。こうした材料は、地元の大社漁港だけでなく出雲や松江の市場からも仕入れて、新鮮で旬の魚を味わってもらえるように準備しているそうだ。
メニューには、出雲大社の大遷宮に合わせて始めたランチメニューもある。その中の松定食は、握り寿司に茶碗蒸し、小鉢、汁物で1,700円(税込)だから、先の握りの並7貫盛りよりお得だよと教えてもらった。また、竹定食は、ちらし寿司に茶碗蒸し、小鉢、汁物で1,500円(税込)となっている。
今回は撮影があるから寿司は器に乗っているが、普段カウンターに座って松定食を頼むと、握りはカウンターの少しだけ斜面になった、つけ台と呼ばれる場所に1貫ずつ出されていく、すると回転寿司に慣れた若い人は食べ方がわからなくて、しばらく手を付けない人が多々いるという。服部さんによると、ここで寿司屋のカウンターデビューする若い人たちが居るという。ちなみに、カウンター内はつけ場、客席はつけ前という。
ある時、横浜から母娘の二人連れが浪花鮓を訪れて言うには、「出雲大社に行った息子に、出雲大社はどうだったかと聞くと、ほとんど浪花鮓さんの話しかしないので、不思議に思ってて、とうとう来て見ました。」と言われたお客さんがあったそうだ。彼もカウンターデビューしたのか、少しご馳走したのか。なにかあったんでしょうね。にこやかに服部さんは言う。
今の寿司屋は、服部さんの父母が昭和49年(1974)に新築して始めたものだそうだ。折しも、国鉄の東海道新幹線開業、大阪万博などがあって、戦後世代が大学を卒業して社会人になる頃のことである。国鉄が1970年に国内の個人旅行を盛んにしようと始めた「ディスカバー・ジャパン」の最中で、出雲大社も観光客が増え始めたころ。それでも、浪花鮓の主なお客さんは、選抜高校野球で昭和35年、36年と連続で甲子園に出場したこともある大社高校野球部のOBのみなさんで、溜まり場になっていたそうである。今のカウンター席は6席だが、当時は10席だったそうで、さも賑やかなことだっただろう。しかし、平成2年に改装した折、服部さん1人でも切り盛りしやすいようにと短くしたという。他には4人がけの座敷が二つ、また座敷の個室もある。
服部さんは、大阪、奈良で修行して、この店を継いで50年。その間には良い時も苦労もあったという。中でも忘れられないのは、2000年前後に大流行したO157で経営は大変になった時のこと。それまで、出雲大社である結婚式には、昼食や持ち帰りにお寿司の折詰めが付きものだったので、1日で600人分作ったこともあったそうだ。しかし、O157を用心して、式場がお寿司の折詰めを辞めてしまい、大打撃となったそうだ。そして昨今のコロナ到来であるが、意外に大社町内から注文される出前が増えたり、持ち帰りのケータリングを希望して来店する人も多くなり、これは打撃にならずに済んだとのこと。最近は、スマホのSNSで見て来た人や友達や知人に勧められて来たという人が多くなったという。取材した日は平日だったが、昼は満席だったという。
旅行が好きな服部さんは台湾や高野山など行った時の話などで、カウンターを挟んでお客さんと話が弾み、リピーターになった人もいるという。「満席になると忙しくて話ができないのが辛いんだよね。」と服部さん。
終わりにメニューには無いコースを紹介しよう。それは、握りと刺身、酢物、天ぷら、焼きものなども出てくるもので、握り中心に食べたいのか、酒の肴が多い方が良いのか聞いて、品揃えする店主お任せコース4,000円(税抜)だ。これは、きっとお話付きであろう。
浪花鮓
営業時間 11:30〜13:30 17:30〜21:00(OS 20:30)
定休日 水・木 (不定休あり)
TEL 0853-53-0260
住所 大社町杵築東385−3
駐車場 5〜6台
浪花鮓 35.397554, 132.685019