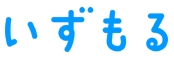7月28日の暑い夏の日曜、島根半島にある片江(かたえ)という漁村に向かった。朝9時、海も空も青々として日差しがきつい、この日は午前中に気温が33度になった。港に車を停め、集落の路地を方結(かたえ)神社に向かう。途中、紺色の法被(はっぴ)を着た人たちに出会う。「おはようございます」と挨拶を交わしながら進んでいくと、左手にあった大きな鳥居の向こうには法被姿の人たちが何十人もいた。
方結神社の鳥居をくぐると、神社の本殿の右横にある歳徳神の宮があり、そこに神輿が2基祀られていて、この日の祭りのお供えがされている。9時半になると女性の神職2人によって祝詞やお祓いがなされ、顔に墨を塗られた法被の男たちが二つの神輿を運び出して宮練りが始まる。漁村の細い路地を二つの神輿が「チョーサヤチョーサ」の掛け声とともに進んでいく。神輿は前に6人、後ろに6人 合計12人で担がれている。この日行く場所は6ヶ所の予定。法被を見ると襟に染め抜かれた白い文字に、片江東歳徳神と片江西歳徳神、そして東西の文字のない片江歳徳神の3種類ある。また、背中に大きく丸に片の文字が染め抜かれた法被姿の中に、亀甲に三柏(みつがしわ)と蔓(つる)が白く染め抜かれ、その紋の下に親當(おやとう)の文字のある法被が1人。この日の祭りを取り仕切る人物である。
昔、片江には歳徳神の宮が東西の2ヶ所にあって、町内を異なるルートで宮練りしていたらしい。それが、数年前に人口の減少から今の方結神社境内にある東の宮の1か所に祀られるようになったという。今では、東西が仲良く二つの神輿を担いでいるのだ。
最初に向かった昔の西の歳徳神のあった場所近くの広場に着くと、一旦、神輿を下ろして休憩なのだが、神輿を追うように墨や御神酒の一升瓶を持った女性陣が到着、そこにあった軽トラックには冷えた缶ビールが積まれていて、それが次から次へと振る舞われた。
次の北の浜の空き地までは、漁村の民家の立ち並ぶ細い路地を、よろよろしながら進む神輿。海岸に出ると海面からの照り返しもあって灼熱の夏、汗だくで顔の墨も流れ出している。そこで休憩となると、またもやビールやお酒がやってくる。顔に墨を塗られるからか、あまり出迎える人もいない印象であるが、近くのゲストハウスでシーカヤックを楽しんでいたカヤックが岸辺に寄ってくると、その人たちの顔が地肌残らず真っ黒に塗られてしまった。塗られた人たちはとても嬉しそうにしている。
神輿が再び持ち上げられ、次の漁協近くの公園に向かう。途中、神輿を見に出て来た年配の女性たちがいて、黒い軍手の女性たちが近づいて話しかけながら御神酒を注いで顔に墨を塗る。これは、竈門(かまど)や風呂の焚き口の煤(すす)を集めて水で練ったものという。竈門神は激しい火の神であると同時に、家を守る神として祀られるもので、この墨付けは魔除けの呪法と言われている。そうと分かっているから大人しく顔に墨をチョコンと塗ってもらうのである。
公園では、お酒や肴に加えて、スイカやトウモロコシが特別に振る舞われたが、これは親當からの振る舞い。実は、この公園の横に親當の家があって、家に神輿か、千木を入れるのだという。ここでは神輿の千木が親當の家に入り、床の間に供えられた。新築や新婚の家があれば、そこにも神輿か千木が入れられて祝福するという。このために、神輿の千木は、屋根から離れていて、千木だけを持つ人がいて、神輿の前を歩いているのである。
公園を出たらすぐにまた隣の漁協で休憩すると、次は集落の東の端に空き地で休憩し、少し港に戻って来て東の浜に神輿は降りて行く。ここまで、出発しておよそ2時間、距離はおよそ2キロメートル。
気温33度の熱波と御神酒が入った体内のアルコールもあるが、神輿の担ぎ手の高齢化もあって、もう神輿はふらふらである。若い担ぎ手の中には、休まず担いでいる人もいるから尚更である。担ぎ手が不足しているのだろう、結婚して家を出た娘さんの旦那さんなども担ぎ手に加わっているようだった。
浜に降りた神輿は、そのまま海の中へと入っていく、全員で禊ぎである。ここで新婚のお婿さんなどが、担がれて海の中でドブーンと投げ込まれたりする。これは新郎の無事を祈る水祝い。海に入った人たちの顔の黒い墨はすっかり落ちて綺麗になっている。
この後、神輿は大人しく担がれて方結神社へと帰って行き、元の宮に収められて夏の歳徳祭(虫干し)が終わるのである。
この歳徳祭はもともと正月に行われていたが、我が国で初めて2艘引きの底引網漁という漁法を、大正時代に生み出した片江漁港には、片江船団と呼ばれる底引網の大船団があった時代があった。その乗組員が正月は遠洋漁業に出ていて祭りに参加できなかったことから、宮の「虫干し」を兼ねて夏にも祭りを行ったのが始まりという。これが戦前の事のようだから、年二回の歳徳祭は、もう90年ほども続いているそうだ。
1997年に発行された『島根半島の祭礼と祭祀組織』(島根県古代文化センター)という調査報告書によると、その調査があった頃には、宮が東西に分かれていて、それぞれの宮練りが巡る場所が各々15か所もあったとある。それがこの日は、東西が一緒になって、回る場所も6か所と大きく縮小していた。現在の片江は6区に別れており、2区ずつ当番がまわってきて、西と東の歳徳神を担ぐので、3年に1回ずつ回ってくるとのことだった。
方結神社 35.560208, 133.189152