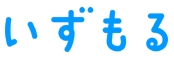雲南市加茂町に低いけれど、とても美しい姿の山があって、通るたびに気になってしょうがなかった。調べてみると高麻山と書いて「たかさやま」と呼ぶらしい。標高は195メートル。場所は、加茂町の中心部にある加茂中駅から1キロメートルあまり東にある山である。出雲国風土記にも載る山で、スサノオの御子である青幡佐草日子(アオハタサクサヒコ)が、この山の上に麻(あさ)を蒔いたので高麻山というとある。
近くにある雲南市大東町の幡屋神社は、歴代の朝廷に「麻布の機職として仕えこの地に住まいした一族によって創建されたと伝えられる」と島根県神社庁のホームページで紹介されていたので、その幡屋の一族とも関連する神話なのかもしれない。なお、アオハタサクサヒコは出雲国風土記の意宇郡(おうぐん)大草郷(おおくさのさと)にも登場している。
高麻山の南側に登山道があったので登ってみた。登山道入り口は大西(だいさい)地区にあった。高麻山には戦国時代に山城、高麻城があった。それは毛利氏と争いながらも中国地方の覇権を約80年間も握っていた戦国大名の尼子(あまご)氏の出城である。尼子氏の本拠地は安来市広瀬の月山にある富田城で、その防衛拠点となる城が尼子十旗と呼ばれていた。高麻城はそのひとつだった。
大西地区は、その高麻城への搦手(からめて)となる裏門があり、小門谷と呼ばれたところ。高麻山の登山口には、出雲国風土記に高麻山として記載の場所であることを表す碑も建っていた。車の轍(わだち)もある登山道は広い。少しだけ登ると、この大西地区や遠くに赤川を望む。距離にして400メートルほど進むと車を回せるほど広い場所があり、ここまでは四輪駆動車なら来れそうだ。
ここから道は細くなり坂も急となり登山道っぽくなったが、道は整備されていて歩きやすい。途中、ところどころに少し広くなったところがあった。山城の曲輪(くるわ)だろうか。曲輪は下から攻め上がってくる敵に向かって、岩を落としたり、矢や鉄砲を撃つための場所である。そんなことを考えながら進むこと、登山口から20分あまりで山頂に到着。距離は登山口から約800メートルといったところ。
頂上に立って見渡すと平坦地は細長く、その中央に祠があって、中に高麻権現と呼ばれるお地蔵様が祀られていた。頂上の周囲は雑木林で展望は望めず残念。この頂上に山城があって、城といっても砦のようなものらしいが。そして東側の祠の向こうの方が御殿平と呼ばれた城主の居館があったところのようだ。さて、出雲国風土記にこの高麻山の峰にアオハタサクサヒコの御魂が坐す。とあるが、祀られているのだろうか。
高麻権現は、明治時代に戦国時代の戦死者の霊を弔うために、大西村の人々によって建立されたお地蔵様だという。ではアオハタサクサヒコの社はあったのかどうかであるが、高麻山の周囲の人々は高麻八幡宮として崇敬していたようだ。高麻城の築城の時に、南麓にある寺上という場所に移されたと言われている。それが、高麻城が落城した後に、再び山頂に復帰したとも言われているが定かではない。高麻八幡宮は明治5年に無格社になったため、明治7年に現在の南大西にある十九社神社境内にある金刀比羅神社に合祀されて、今も存在する。
この一方、高麻城の築城の時に高麻城の北西側にある高麻谷側にも、高麻八幡宮が建立されたようで、アオハタサクサヒコの御魂を慕っていた高麻山の北西側の加茂村の人々によって祀られた。つまり、当時、高麻山を降りた高麻八幡宮は大西村側と加茂村側の二つに別れたことになる。両村の住民の崇敬を集めていたのだから、山頂を去るにあたって、それぞれの村へ向かって降りたのだろう。
そして、加茂村に降りた高麻八幡宮は、江戸時代の棟札などからも継続して存続していたが、明治12年、山頂への復旧願いを島根県に提出して許可され、山頂に復帰した。しかし、それがいつのころか不明であるが、高麻山の北西側の麓に字も屋号もタカサの家があり、そこと山頂の間の山中に移転して、祠と鳥居があった。毎年9月15日には、そこへ加茂神社宮司を迎えて祭りを行なっていたという。しかし、令和になって、加茂神社(出雲国風土記に見える屋代社)境内に移転され、本殿の後方西側に鎮座して今を迎えている。
出雲国風土記には、高麻山の北側には樫や椿の木があり、他の三方は野なり。とあって草原だったようだ。農耕に牛が活躍した頃には、その餌となる草刈り場でもあったという。また、加茂小学校の周囲は湿地帯であったが、江戸時代に高麻山の北西山麓の砂を使い、16年がかりで埋め立てたという。それによって加茂の町が大きくなったのだから、高麻山の恩恵は計り知れないものと思われる。高麻山の山頂には昭和50年ごろまで、松の大木が茂っていて、周囲からもよく見えていたという。それはマツクイムシの被害で消え去ったが、今でも周囲からは秀麗な富士山型をした高麻山の姿を望むことができる。(ライター 三代隆司)
参考資料
加茂町誌 昭和59年 発行 加茂町
南大西とんとん史 平成4年 発行 南大西郷土史編纂事業体
中村上自治会誌 昭和62年 発行 中村上自治会
ふるさと南加茂誌 平成7年 発行 ふるさと南加茂誌編纂会
砂子原誌 平成2年 発行 砂子原自治連合会
三代郷土誌 平成12年 編集者 三代郷土誌編集委員会
加茂町史考 著者 中林季高 昭和30年 発行 加茂町史考頒布会
加茂神社正遷宮記念 棟札集 平成18年 編集 加茂神社遷宮委員会
この 高麻山 に関してGoogleMapで検索できる緯度経度を以下に示します。
高麻山 35.346417, 132.925525
高麻山 登山口 35.341090, 132.921085
十九社神社 35.334543, 132.917864
加茂神社 35.347727, 132.908333