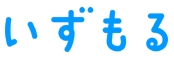島根県は古代より製鉄を行う たたら操業 が盛んなところとして知られているが、その主な場所は、菅谷(すがや)たたらのある雲南市やたたら操業の技術を現代に継承する「日刀保(にっとうほ)たたら」のある奥出雲町など、山間部の地域がよく知られている。ところが、日本海からわずか700メートルほどの場所で、およそ150年に渡ってたたら操業をしていた場所があった。
そこは越堂(こえどう)たたらと呼ばれ、展示施設がオープンしたというので行ってみた。出雲市の北西部にある人気の道の駅キララ多伎を過ぎておよそ6キロメートル、車なら約10分もせずに道路が海と同じような高さになってきたら、そこが江戸時代に鉄を船で運び出した港のあった田儀港である。そこからそのまま大田市方向におよそ500メートルも進むと国道9号の東側、田儀川の辺りに国指定史跡の越堂たたら跡があった。
たたら操業をして鉄を生産する場所には、復元模型が作られており、およそどんな感じのものか分かる。幅約1メートル、長さ約3メートルの製鉄炉とその両側に、炉に風を送る天秤ふいごが2基設置されている。宮崎駿監督のジブリ映画「もののけ姫」をご覧になった方なら分かると思うが、あのアニメ映画に登場した、たたらを踏む女達というのは、この天秤ふいごの上に乗って板を踏み、炭を熱く燃やすため炉に送風する仕事をしていたのだ。
たたらは大量の炭を燃やし、そこへ天秤ふいごで送風して高熱にし、その上から砂鉄を少しずつ落として、赤く焼けた炭の上で砂鉄が溶け、炉の下に集まって大きなケラと呼ばれる鉄の塊となるものである。砂鉄は、良質な砂鉄を含む花崗岩の山を崩して、その砂の中から砂鉄を分け取る。そして炭は、近隣の山の木を切って炭にしたものを使う。そのため、10数年から30年ほども稼働すると近隣の山々に炭にできる樹木が無くなるため、たたら場は移動する。ところが、越堂たたらは、およそ150年間も同じ場所で操業したことが分かっている。これは、なぜかというと、炭や砂鉄を船で田儀港へ運んできて、それを使って操業していたからである。
越堂たたらを操業していた田儀櫻井家の本拠地は、越堂たたら跡からおよそ6キロメートル、車で15分ほど山中に入った場所で、宮本鍛治山内(みやもとかじさんない)遺跡として保存されている。山内とは、たたら操業施設とそこで働く人々の居住区が一体的に整備され配置された集落のこと。
ここでは、たたら操業をしたのではなく大鍛治場を操業していたようで、近隣の山々でたたら操業して生み出した鉄、主に刀の材料にする玉鋼(たまはがね)ではなく、銑(ずく)と呼ばれる炭素の含有量の多いものを大鍛治場で炭素量を下げる作業を経て割鉄という鉄の棒に加工して出荷していたという。割鉄は包丁鉄とも呼ばれる。割鉄は包丁や鎌や鋤を作るのに必要なものだったため、田儀港を経由して日本各地へ出荷された。
田儀櫻井家の生産量は、たたら操業を許された鉄師の九家の中で、生産量トップの吉田村の田部家と競うほど多かった。しかし、明治15年に宮本鍛冶屋から出火し、本宅をはじめ山内の70戸が被害に遭ったため、8年後の明治23年(1890)に、田儀櫻井家は約250年続けた、たたら製鉄業の経営を断念して宮本を去ったのである。
越堂たたらの操業では、砂鉄は石見(いわみ:島根県)因幡(いなば:鳥取県)、伯耆(ほうき:鳥取県)から、炭は島根半島の鵜峠(うど)や鰐淵寺から取り寄せていた。ある時、砂鉄の入手先に困って、田儀港の北西13キロメートルほどの神戸川河口あたりにある西園から砂鉄を仕入れたことがある。この砂鉄は、中国山地の山々の砂を流して来た河川によって、日本海に注ぎ、そして砂浜に打ち上げられたもの。国引き神話で知られる白砂青松の広がる園の長浜には、今でも、そうした砂鉄の積もった層を見ることができる。
越堂たたら跡 35.265018, 132.582470
田儀櫻井家たたら製鉄遺跡 35.236033, 132.616081
田儀港 35.271473, 132.580366