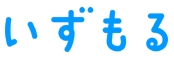最近になって、「山中に海、船の文字」で取り上げたウノヂヒコノミコトに関連する場所が、海潮神社の他に5ヵ所あることが分かった。それを紹介する前に、海潮(うしお)を振り返ると、「ウノヂヒコノミコトが父親のスガネノミコトを恨んで、北の方の出雲の海潮を押し上げて、父神を漂流させ、その海潮がここまで来たので、得鹽(うしお)と云う。」というように地名由来として語られていた。
→「山中に海、船の文字」
『出雲国風土記』にある記載の場所を尋ねてみよう。まず、大原郡の項にある宇乃遅(うのじ)社に当たる宇能遅(うのじ)神社である。先の雲南市大東町の海潮神社のそばを流れていた赤川を、およそ15キロメートル下ったところにある。雲南市加茂町の加茂柳橋の西詰め北側の土手の下に鳥居が見える。その鳥居の前にある大きな石柱に宇能遅神社と刻まれている。拝殿にまっすぐ伸びる石段を進むと拝殿の軒下に社名の扁額ではなく、由緒書がかかっていた。そこには、祭神として、宇乃遅彦(ウノヂヒコ)命と父親の須我禰(スガネノ)神の神名があった。
近くにもう一つ関連する神社がある。『出雲国風土記』にある汗乃遅(うのじ)社と言われており、先の宇能遅神社から南東へ直線で3キロメールほどのところにある須美禰神社である。これは、『雲陽誌』の大原郡立原の項には、宇治明神とある神社とのことで、主祭神は須我禰命である。このように、ウノヂヒコノミコトの神話に関連する神社が、赤川の中流域に二つあるのだ。
そしてもう一つは、神社ではなく地域のことであるが、『出雲国風土記』の楯縫郡沼田郷に、ウノヂヒコノミコトが「湿地の水で、干した米を柔らかくふやかして食べることにしよう」と言ったとあり、『出雲国風土記』の国引き神話に登場する去豆(こず)の折絶(おりたえ)のある地域、今の出雲市口宇賀町あたりにウノヂヒコノミコトの足跡があった。
『出雲国風土記』の研究者の関和彦氏は、ウノヂヒコノミコトは海にかかわる神で、それも「海路(うのち)」の意と解するとしていて、古代の塩の道と解き明かしている。
出雲大社の近くの稲佐の浜には、塩掻き岩なる出雲大社の神事に使う塩を掻き取る岩もある。赤川は、「ヤマタノオロチ伝承(1)」 で取り上げた草枕山のところで斐伊川に合流し、その斐伊川は古代には斐伊大河(ひのおおかわ)と呼ばれて出雲大社の付近の日本海に注いでいたのだから、その大河を遡り塩が運ばれて行ったのだろうか。
→「ヤマタノオロチ伝承(1)」
一方、沼田郷の奥にも日本海がある。風土記の時代には許豆(こづ)浜という広さがおよそ200メートルに及ぶ浜だったようである。今、その浜は埋め立てられて大きな港となっているため面影も感じられない。しかし、50年ほど前ごろまでは砂浜であった。筆者はこの許豆浜のある現在の小津に母親の里があり、小さい頃には、よくその浜で泳いだり、ウナギ釣りの餌になるゴカイを獲ったりしたことがある。親戚が持っていた古い写真には、弓なりに伸びた浜に船が陸上げされている。古代、ここで作られた塩が得鹽(うしお)へ運ばれたのだろうか。
さて、ウノヂヒコノミコトについては気になる説があった、出雲大社の瑞垣の内にある東側の門(みかど)社に祀られる宇治神がウノヂヒコノミコトのことではないかとも言われている。スサノオがイザナキに「海原を治めよ」と言われたことと関連するのかもしれないと思ったりする。
なお、須我禰(スガネノ)命をまつる他の神社も上げておくと、いずもるの「スサノヲ夫婦の新居は和歌発祥の地」で取り上げた須我神社は、その昔、須我神社の近くにあった海潮神社を合祀したことが分かっている。
また、海潮温泉桂荘の近くにある古代鉄歌謡館の後ろにあって、赤川に隣接する奥田神社には、須我禰命が祀られている。そして、現在の海潮神社の近くには、「海潮押しとめ池」があったという言い伝えがあるそうだ。古代の海潮一帯は、須我禰命と宇乃遅彦命を祀る地だったのではないだろうか。
宇能遅神社 35.343982, 132.904017
須美禰神社 35.326752, 132.932858
海潮神社 35.333110, 133.026521
許豆浜(小津漁港)35.455819, 132.759048
須我神社 35.354229, 133.031565
奥田神社 35.326817, 132.992784