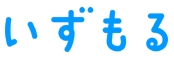正月、小伊津の歳神祭りが4日に終わり、次には12日の夕方にトンドさんがあるが、その神木竹迎えが昼過ぎにあるという。なにやら秘めたる行事の香りがする神木竹迎えは、トンドさんで燃やす竹を山に切りに行く行事だという。お願いして、神木竹迎えに参加させてもらった。12日の昼下がりに小伊津自治会館に集合した参加者10人余りは、それぞれに長靴や軍手や帽子を身に付けていた。
車に便乗して5分ぐらいで目的地の竹山に到着した。作業の前にお清めとして、小さな紙コップに入った御神酒と梅干しが配られた。それらを口にしていると「この竹だ」と道路の下の方から声がした。前もって下見のしてあった目当ての竹は、道路から数メートル下の急傾斜の場所にあるようだ。竹を伐り出しやすいように、銘々が周りのツタや枯れ木を取り除きはじめていた。
とそこへ「歌でも出るといいけどなあ〜」、「うれしめでた〜の若松さまよ〜」という民謡、花笠音頭の冒頭だけが聞こえたかと思うと、ノコギリで竹を切る音が聞こえて来た。
5年ぶりだから省略されたのか、本来なら、神木竹をとるときに、竹の根元に酒を注ぎ、山の神と竹に対して「伐らせてもらいます」とお願いして、「うれしめでた〜の若松さまよ〜」を歌いながら伐ったものだそうだ。
無事に伐り出された20メートルはありそうな長い竹は、葉の部分には菰(こも)を巻かれ、数人で担ぎ上げられて、海沿いの起伏と湾曲のある道路を、途中休み休みしながらおよそ2.5キロメートルも離れた小伊津漁港まで運ばれた。
港に運ばれた竹は、およそ半分の11.5メートルに切られてしまった。以前は、15メートルあったそうだが、飾りを減らしたため、風の影響を考えて短くしたという。漁港の中央部分にトンドさんのために小石が敷き詰められた場所があって、そこに高さ2メートルほどの太い柱が穴を支えに立てられていた。丸い扇の飾りと五色のテープのつけられた竹は、支えのロープなどを巧みに操作して、一気に立ち上げられ、太い柱にくくり付けられた。日本海の強い風に五色のテープが引きちぎられて、二色になって風になびいた。
港が薄暗くなり始めた夕暮れ5時半になると、持ち寄られた正月飾りなどが1メートル以上も積み上げられたトンドさん。そこへ、若松屋という提灯を下げた一行が現れた。その先頭の人の出(いで)たちは、羽織袴で、正月に潮清めをしていた屋号、若松屋さんである。手にはあの潮タガを持っている。その数人の一行は、そのまま海岸の水際へと降りて行き、まず潮タガに海水を汲み、そして、若松屋さんは羽織袴と肌着も脱いで素っ裸になって海に浸かった。禊(みそぎ)である。
それが終わると再び羽織袴に身を包み、若松屋の提灯とともに、トンドさんを右回りに回りながら潮タガの潮をトンドさんに向かって振り撒いて行く。終いには、トンドさんの一角に藁が積まれたところがあって、そこへしゃがみ込むと、別の人が後ろから呉座(ござ)を被せた。すると中から、カッ、カッ、カッと音がする。なんと火打ち石で火を付けるのだ。間もなく、呉座の上から白い煙が見え始め、呉座が取り除かれると大きな炎が立ちのぼった。トンドさんがまたたく間に火につつまれていくと、トンドの竹は倒された。火は強い風に煽られて一層勢いよく燃え盛る。以前は、ここで各戸から正月の餅を持ってきて焼いて食べたそうだが、餅を包んだアルミホイルが分別ゴミ処理に相当するため、いまでは餅も焼かなくなったという。近寄ると服が焼けそうなトンドさんのそばに集まって焚き上げ、火の熱を体に浴びる。老いも若きも皆の顔が炎に照らされて明るい。
この祭り、昔は、頭屋(御宿)と称する家を住民の中から選び、氏神である三社神社境内にある歳徳神社祠に納められた神輿を、神様として頭屋に迎えて安置して、それを中心に祭りを行っていた。
昭和の時代には、神木竹と一緒に頭屋の門松にする神木も切り出していたが、頭屋は1990年から小伊津自治会館になっており、門松は12月の暮れに別の場所で取られて、自治会館の玄関に飾られていた。つまり、もともとは神木、神木竹の切り出しから門松を飾り、餅をつき、潮清め、神楽、トンドさんまでが一体となって頭屋を中心として行われた十数日間の祭りであった。それが数日間の祭りになり、2010年の正月からは、その祭りも分けたのだそうだ。時代が変わるに連れて、祭りの様子も変わっていく。それを目の当たりにしているのだった。(ライター 三代隆司)
※本願
この小伊津の祭りには、祭りの発起者とされる本願主がいる。「若松屋」という家が古来より「本願」とされてきた。若松屋さんが腰にさした脇差を納めた木製の箱があって、その蓋の表の箱書きに「御歳徳善神金築惣八」、蓋の内側には「寛政十二年庚申左義帳」とあり、他に「歳徳神様のかさりに此の脇ざしをさして永代火わたすことを私家の主人により外ニハ相ならさる事〜」とある。現在の当主の若松屋こと金築さんによると、「先祖の惣八が北前船に乗船していたらしく、他の土地から持ち帰ったお祭りのようです。」とのことだった。寛政十二年は江戸時代後期、西暦1800年のことである。
参考資料
神の国の祭り暦 著者 勝部正郊 発行 慶友社 2002年
神去来 著者 石塚尊俊 発行 慶友社 1995年
ここに登場する 小伊津漁港 に関してGoogleMapで検索できる緯度経度を以下に示します。
小伊津漁港 35.502498, 132.839130