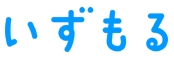出雲市駅から北へ向かって500メートルほど行くと、一筋の川が東から西へ向かって流れている。川の名は高瀬川。そこに架かる橋は三京橋という。この川は人の手で造った運河である。昭和30年代、三京橋から600メートルほど下流にある海上地区に住んでいた私にとって、高瀬川は格好の遊び場で、フナ、ハヤ、ウナギ、カニなど魚取りに興じた。夢中になって川を遡り、三京橋まで来たことがわかると引き返したものだった。
今も清らかな水の流れる高瀬川を造ったのは、三京橋に銅像が立つ大梶七兵衛である。完成は江戸時代初期の貞享4年(1687)という。目的は、七兵衛が先に開拓した荒木浜の灌漑であり、松江藩としては藩の米の輸送にも使いたかった。高瀬川の起点は三京橋から東へ約4キロメートルの来原岩樋(くりはらいわひ)である。岩樋から川の水が勢いよく流れ込んで、高瀬川を下っていく。水を供給する斐伊川は、川幅が500メートルほどもある大河と呼ぶにふさわしい天井川で、古事記にはスサノヲがヤマタノオロチ退治をした神話に登場する川である。出雲平野を生み出した川と言っても良いだろう。
その川の水を、遠く10キロメートルあまり離れた荒木浜まで届けようという運河であり、船まで浮かべようというのだから、当時としては大工事であった。伝聞される工法は、水漏れを防ぐために川を掘ったら、まず筵(むしろ)を敷き詰めて、その上に粘土を突き固めたらしく、昭和の改修工事の時に、両側の壁を壊すと厚さ30センチぐらいの粘土壁があったという。工事では、それがコンクリートや石・ブロックの壁に改修された。
延長11.4キロメートル、江戸時代の飢饉救済の土木工事にもなったようだが、完成するには4年の月日を費やしたそうだ。不思議なのは、現在の来原岩樋と高瀬川の末になる川尻の標高差をみると約10メートルである。測量機も無い時代に、長さ100メートルで約10センチメートルの下がる勾配をどうやって測ったのか、闇夜に提灯をつけて、それを見通して判断したと伝わるというが、そんなことでできると思えない、どんな工夫をしたのだろうか。
また、川筋は出雲市の北に聳える山並みの東の峰にあたる旅伏山に登って判断したと伝わる。しかし、実際に登ってみればわかるが、高瀬川はかなり遠くに流れており、眼下というには程遠いため、それは極めて大雑把なルートだったと思われる。
来原岩樋から5キロメートルほどのところで高瀬川は只谷川という排水路と並行して流れている。この排水路は昔からあったと考えられていて、排水を流す川であるため、高瀬川の川床より2メート以上も低いところを流れている。この只谷川を横切るなどせずに、並行させて流すことは、当初から考えられていただろうと言われている。
来原岩樋からおよそ6キロメートルの高松小学校あたりから、川幅が狭くなってくる。主に戦後の自動車の普及によって道路幅を広くするために川幅を犠牲にしたと思われる。
来原岩樋から8キロメートルほど来たところで、新内藤川の上に高瀬川を流すための橋(当時は木製釣樋)が架かっている。新内藤川を高瀬川は吊り橋のような形で渡って流れていたという。その橋も川舟が通るために、幅が5メートルほどもあったのだろうか。
高瀬川の終点にある川尻に行ってみると、その昔、高瀬川を登り下りした高瀬船が展示されていた。実際の船の記録が残っておらず参考までの大きさとのことだが、長さ14.4 メートル、幅2.1メートル、高さ0.6メートルと説明されていた。この船が上り下りすれ違うわけだから、川幅は最低でも5メートルぐらいは必要と想像された。
私が遊んでいた海上地区の橋から300メートルほど下流に、「菩提寺の船元(舟溜り)」と書かれた板看板があった。よつがねふるさと史跡と記され、そこには達筆で「高瀬川は、かつて舟で物資を運ぶ運輸機関の一つであった。江戸時代の一時期、松江藩のお登米も輸送していた。後には、薪、瓦、人糞尿(肥料)に変わったが、昭和十年代まで物資の輸送に使われていた。藩政時代は、神門郡に三七艘の高瀬舟があり渡橋村には三艘あった。この辺りは舟溜りで物資の集積集荷する「みなと」で当時は賑わっていた。」(句読点追記は著者)と丁寧に解説されていた。下る舟は竿で進み、上る舟は、岸辺から綱で引いて進んだらしい。
川尻には荒木川方という松江藩の役所がおかれ、蔵が立ち並んでいて広さは1万1千平方メートルもあったというから広大で、今ではその敷地内にあった稲荷神社が、川方稲荷神社として名残をとどめている。
今回、高瀬川を来原岩樋から自転車で巡ってみたが、高瀬川沿いは自転車道になっていて、川沿いには公園があったり、住民の花壇があったり、川辺の桜や柳も美しく、人々の暮らしに潤いを与えているように思えた。(ライター 三代隆司)
参考図書
大梶七兵衛と高瀬川 石塚尊俊 著 1987年 発行 出雲市教育委員会
大梶七兵衛翁 高瀬川開削三百年記念事業実行委員会 編集 1989年 発行
大社町史 中巻 2008年 発行 出雲市
大社町史 下巻 1995年 発行 大社町
この 大梶七兵衛の高瀬川開削 に関してGoogleMapで検索できる緯度経度を以下に示します。
来原岩樋 35.354622, 132.786276
大梶七兵衛銅像 35.365356, 132.755634
只谷川 35.362359, 132.742255
新内藤川を渡る高瀬川35.364808, 132.710361
川尻 35.385927, 132.683353(松江藩荒木川方跡)
大梶神社 35.378063, 132.683150
八通山林 35.379583, 132.683008