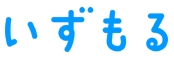松江市八雲町には、日本の国産み神話で知られるイザナミノミコトの埋葬地の一つと想定されている岩坂陵墓参考地があるが、そこからわずか3キロメートルほど南の山間部に入ったところに、姿の美しい山がある。以前から神が隠れ籠るといわれる神名火山ではないかと気になっていた山である。昔は、麓に神社があって、山の名は、室山(むろやま)と聞き、ますます神名火山らしい山だと分かったので、調べてみた。
すると、山には、出雲国風土記に載る宇留布(うるふ)社があったようで、山も松江藩の地誌『雲陽誌』(1717年)には宇留布山とあった。その宇留布山の南麓の畔室(あぜむろ)地区にある民家の横から入って雑木林の中を登っていくと、一度開けて、次に入った杉林を少し進むと、白い御幣が目に入って来て、その御幣で祀られた石碑には、宇留布総荒神とあった。その左手側に神社があったという。目をやると石垣が積み上げられた内側には広い平地があって、そのずっと奥の方の山際にも石垣が見えた。ただ、あちこちに木が茂って荒れ果てていた。現在の宇留布神社は、そこから南西の方角に1.5キロメートルほどの場所に鎮座している。明治十四年にここに遷って来たという。
『平原風土記』に載る宇留布神社の由緒記によると、「旧号宇留布神社と云う。三島大明神とも申す。大山祓命(オオヤマハラエノミコト) 木花開耶姫命(コノハナサクヤビメノミコト) 当社は延喜式に宇留布神社とあり、社地は宇留布山(室山)の半にして、一間四方の神楽所あり、その内に一尺四方の山祠あり、鳥居一基、境内は三十五間に二十五間。社伝には、古は大社にて宇留布山一円が社山なり、宇留布輪という田圃も社有の由。」とあった。今、その境内地を示す白い木柱が立っているが文字は消えてしまっている。足立岩一という地元のお寺の住職がまとめた『平原風土記』に載る写真を見ると、「出雲風土記登載 宇流布社跡」と書いてあったことがわかる。
大山祓命は大山祇神(オオヤマヅミノカミ)と同神で木花開耶姫命とは父娘の関係である。出雲神話で有名なスサノヲの妻となった櫛名田比売の父母であるアシナヅチ、テナヅチも大山祇神の子であり、木花開耶姫命とは兄弟姉妹となる。
『平原風土記』には、古老の伝説として、この宇流布社跡の前に小池があって、木花開耶姫命が父神のために、その清水で酣酒(甘口のお酒か?)を造ったという。その池は神社のすぐ近くで神社に向かって左方の古い池だという。別の資料では、これが瓢箪(ひょうたん)の形をしているので、瓢箪池とも呼んだという。
また、木花開耶姫命が酒の元になる水として幾度も汲んでいると、いつしか水が酒となって湧くようになった。と伝わっている。しかし、あるとき宇留布神社のこの池に、女が牛を引いて通りかかった。そのとき牛が池に口をつけたために酒がもとの水になったしまったという。このような伝説のある池の水は、水質に優れていたため地元の熊野や松江の造り酒屋がこの池の水を酒の仕込み水として使っていたという。
今回現地を探索したが、草が私の背丈ほども伸びて茂っていて、池が有るのか無いのかさえ分からなかった。しかし、神社の下の方では、室山の南麓を流れる平原川へ、山からの清水が滴り落ちていた。
その平原川には鰻がたくさんいるという。それは、地元の人々が神社のお使いの白鰻が平原川に住んでいるから、鰻を一切獲らないし食べないからだと。その上、地元の人々は、このことを知らない人が鰻漁をしていると、それらの人に時には日当を与えて追い返していたという徹底ぶりであった。宇留布神社の祭神、大山祓命は蛇と関係があるともいわれており、その蛇が鰻に例えられてしまったのではないだろうか。
面白い話は、まだあって、近くの岡ノ目池に伝わる蛇にまつわる伝説があることをはじめ、木花開耶姫命の姉神の磐長姫命(いわながひめのみこと)を祀る社、築貫(つきぬき)神社が室山の東麓にあり、そこは椎の巨木が立ち並ぶ鎮守の杜となっていた。そこの伝説は「木花開耶姫命と一緒に嫁いだ瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が磐長姫命だけを父神のもとに返されたため、磐長姫命は安住の地を求めて旅立った。その国巡りの末に海の入江の尽きた所に舟が着いた。そこで、ここを「つきぬき」と呼ぶようになった。船の付いた場所は、今「舟窪(ふなくぼ)」とよぶ沼田であって、「神田」として一切の不浄と女人を入れぬことになっているという。
さらには、この宇留布神社は江戸時代に三島明神と呼ばれていたが、宇留布神社の鎮座していた室山は字三島、旧社地も字三島、瓢箪池の近辺が字三島前、室山周辺の田は三島神田と土地台帳にあって、畦室地区には三島姓がとても多い。その、三島がなんと、出雲大社の宮司家の祖先にあたる三嶋足奴命から来ており、この宇留布神社は出雲国造が奉斎していたのではないかとする説もある。室山の南には熊野大社、北には神魂神社があり、出雲へ移る前の国造家も神魂神社の近隣に所在していた。
最後に室山の頂上の西側下に磐座と思われる屏風岩があって、山頂は修験道の修行場だったといういい伝えもある。平成時代の中頃までは頂上へ登れて、見晴らしも良かったようだが、今そうした道は失われてしまっている。(ライター 三代隆司)
この ここにも神名火山の山容が に関してGoogleMapで検索できる緯度経度を以下に示します。
現在の宇留布神社 35.396645,133.060182
室山 35.406381, 133.077910
宇留布神社跡 35.404109, 133.075644
築貫神社 35.406260, 133.086631
岡ノ目社 35.399318, 133.101773
参考図書
平原風土記 著者・出版 足立岩一 1983年
出雲風土記とその社会 著者 佐野正巳 発行 雄山閣 1989年5月
八雲村誌 著者 八雲村誌編集部 発行 八雲村 1998年12月
むらの山々 著者 石倉諒一 出版 石倉文晴 2002年3月
八雲村平原の郷 著者 横川信之 出版 横川長流 2005年1月