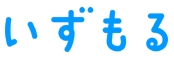出雲国風土記ができたころの今からおよそ1300年前、この出雲地方には、今もある中海と宍道湖の他に、神門水海(かんどのみずうみ)という呼ばれる湖のあったことが知られている。その範囲は、神門水海の名残である出雲市の西にある神西湖から出雲ドームあたりまで広がっていた。今は埋まってしまった神門水海の岸辺を探して歩いていたときに、「延宝五年 荒木浜開拓ノタメ〜」と刻まれた墓標に出会った。
墓標のあったところは出雲市大社町の中荒木地区、神戸川の河口に接する場所である。続けて刻まれていたのは「知西寺ト檀家ノ我ガ大熊家ヲハジメ四家ガ窪田村ヨリ現在地二移住シタ」とあった。窪田村とは、中荒木から南の山中、距離は15キロメートルほどのところにある佐田町の窪田地区のことだろう。窪田地区には、出雲大社の遷宮に際して造営のための巨大な杉の木を産出した吉栗山(よしぐりやま)があることで有名だ。延宝五年は西暦1677年、江戸時代のはじめのころである。その時代に山奥からなぜ寺と一緒に移住して来たのだろうか。
いろいろ調べてみると、知西寺(ちさいじ)を窪田から中荒木に移転させたのは大梶七兵衛という人物だった。彼は、今も出雲市の中心部を流れる高瀬川と呼ばれる運河を江戸時代に開削したことで、地元では偉人としてとても有名である。当時は幅2間(3メートル60センチ)、長さおよそ2里(8キロメートル)もある松江藩第一の船も上り下りした長大な運河を造った。その七兵衛は高瀬川開削事業よりも前に中荒木で開拓事業を行っていたのだった。
江戸時代のはじめの頃の中荒木は、日本海からの強い西風が吹き付ける土地で、海岸から大量の砂が運ばれてくる水の少ない荒地だったという。そこで、七兵衛や馬庭佐平太などの志ある者たちが、荒木浜の開拓を松江藩に願い出て、延宝2年(1674)に先の二人が藩から開発棟梁人(とうりょうにん)を任ぜられ、藩から御褒美として空き地において1町(約9900平方メートル)四方ずつの土地を御免地として下された。御免地とは租税を免除される土地のこと。
七兵衛がまず取り掛かったのは、荒地の開拓ではなく、海岸から飛んで来る大量の砂を食い止めることだったという。現在の中荒木には、北側にある堀川の河口から南側の神戸川河口まで、約1.5キロメートルにわたり大きく2群の松林の列がある。海岸側が湊原山林、西側が八通(やとおり)山林と呼ばれている。七兵衛は、飛んで来る砂を止めるために、その八通山林を作ったのだった。
その方法は、松を植える前に、砂丘に柴で高さ4尺(1メートル20センチ)ほどの垣をつくって砂を止め溜め、砂が溜まるとその上にさらに7尺(2メートル10センチ)ほどの柴垣を作って、そこへ砂が溜まるとまた柴垣をつくるということを何度か繰り返して、砂壁というか砂山を作った。ある程度砂が溜まると、海岸のやせた土地にも育つグミや葦(あし)などを植えた。こうして土地が固まると、そこでやっと松苗の植樹を行ったという。これを長さおよそ1.5キロメートル、幅500メートルほど、面積にして約75ヘクタールに渡って行ったという。
松苗は、神戸川の中流域にある乙立(おったち)の山で生産し、根には育成した土地の赤土を12センチ角程度付けておいて、それを植え付ける時に、根元に赤土を1升(1.8リットル)ぐらい入れたという。これによって、およそ10万本(8万5千本や7万5千本の説もある)の松を75ヘクタールに植樹したと伝わる。ちなみに75ヘクタールの土地に松苗を2メートル50センチおきに均等に植えようとすると、およそ9万本の松苗が必要となる。
七兵衛が知西寺を荒木浜の一角に遷座させた延宝5年(1677)に、自らも松の植樹と開拓のため荒木浜に移住した。(荒木浜は開拓が終わってから付けられた3つの地名である古荒木、中荒木、北荒木よりも以前の土地の呼び名である。)移住した年の年末には、藩より荒木浜に湊新町という港湾交易の町を作るための特例が降された。湊新町において中国山地の藩の米を集荷して出荷することを目的として米蔵を建てることや斐伊川から川船の通る運河のことに触れて、町の建設に銀20貫目(現代のお金にして4000万円ぐらいか)を貸し付けることなどが書かれている。これは、商人を集めることだけでなく、開拓する農民を集める目的が強かったようだが、当時、神門郡奉行であった岸崎左久次(さくじ)が取り仕切って、町づくりも始まった。町づくりの方は、馬庭佐平太が受け持ったと考えられている。
多い時には50軒あまりの家ができたが、町づくりが頓挫したため家が十数軒になった時もあったようだ。しかし、寛延3年(1750)の検地の記録には、3地区の中の中荒木地区だけで、地味が劣る開発間もない新田が90ヘクタール、農家をはじめ寺院や神社の人、医者などを含めて139軒、711人が居住していたという。この検地の記録に、湊百姓四人之者へ御免地として5反9畝12歩とあって、この四人之者が知西寺とともに荒木浜開拓に移住してきた大熊家(墓標の家)、柳楽家、曽田家、川上家の四家で、開拓の労苦を乗り越えた模範となる農家だったのではないかと思われる。
八通山林には、地域の功績甚大な七兵衛を祀る大梶社があって、その後方には、八通山林の遊歩道が続いている。歩むと枯れ松葉がふかふかして気持ちよい。松ぼっくりがたくさん落ちており、その間に小さな松苗が自生していて、最初は人の手で作られたとは思えないほどの松林となっている。八通山林の名は、松の木を8列に植えたからとも伝わっているが、8列どころではない松の数だった。(ライター 三代隆司)
※岸崎左久次 出雲国風土記の調査研究もしており、『出雲風土記抄』を著している。また、松江藩の『免法記』・『田法記』を作成したことでも知られる。
参考図書
大梶七兵衛と高瀬川 石塚尊俊 著 1987年 発行 出雲市教育委員会
大梶七兵衛翁 高瀬川開削三百年記念事業実行委員会 編集 1989年 発行
大社町史 中巻 2008年 発行 出雲市
この 大梶七兵衛の荒木開拓 に関してGoogleMapで検索できる緯度経度を以下に示します。
知西寺 35.373088, 132.689314
八通山林 35.379583, 132.683008
大梶神社 35.378063, 132.683150